
※この記事では内容に広告・プロモーションを含みます
7月から新しい職場でも委員会に入ることになり勉強会を担当
フロアの年間目標は認知症ケアを深める。これに則した勉強会をしないといけません
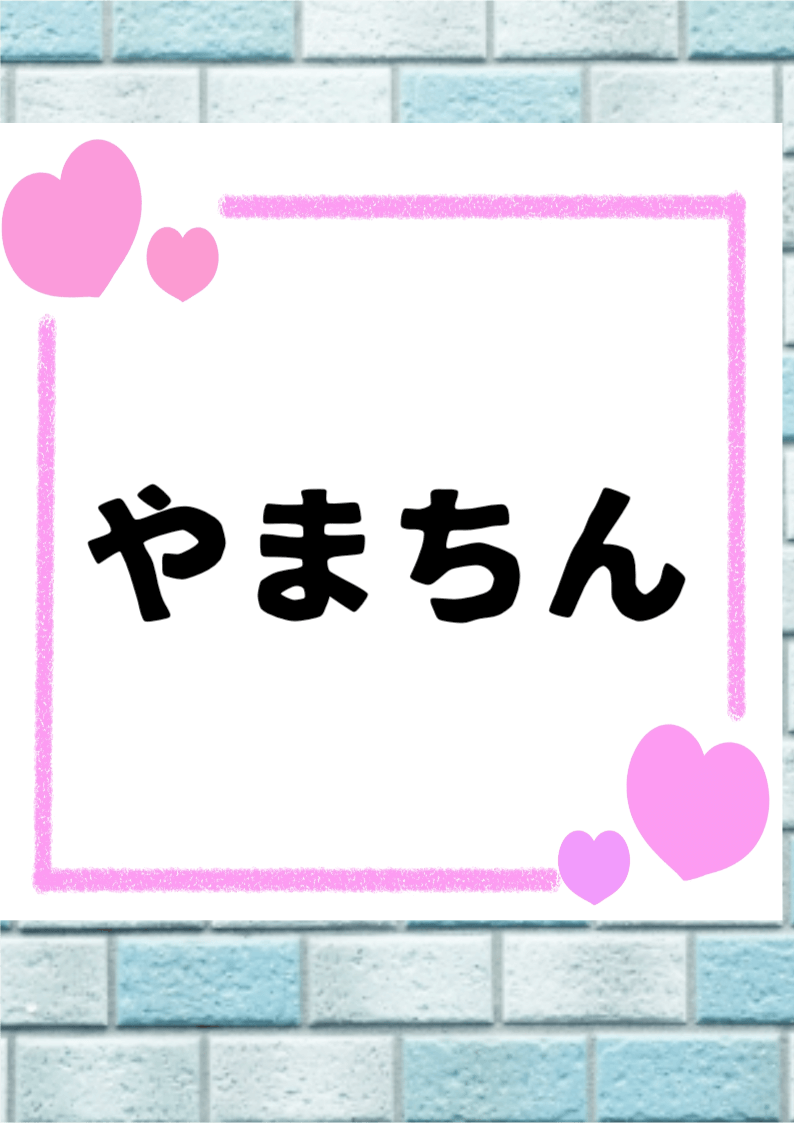
めっちゃ、ザックリですやん
そこで僕は認知症ケアツールのセンター方式をやることにしました
センター方式については、こちらから
そして勉強会のペアになったスタッフからは『認知症世界の歩き方』の本を資料に勉強会をしたいと話があったのですが、僕はそのタイトルは初耳。調べたら2021年9月刊行で14万部も売れているじゃありませんか!?
そこで自分も読んでみたいと思い早速購入
今回はそんな『認知症世界の歩き方』のレビュー記事になります
それでは、いってみましょー ( ̄^ ̄)ゞ
書かれた背景
〜「本人」の視点で認知症を知ることのできる本〜
これまでに出版された本やインターネットで見つかる情報は専門職や介護士視点の難しい言葉で説明したものばかりで、ご本人の視点からまとめられた情報がほとんど見つからない
そこで実際にインタビューを重ねることで「語り」を蓄積することから始めたそうです
ご本人の視点から認知症を学び、生活の困りごとの背景にある理由を知ることで
「どうやって認知症とともに生きるか」
つまり
「付き合い方」や「周りの環境」は変えることができる
人をみて生活をともに作り直す
そんな視点からできるアプローチもある
認知症とともに、幸せに生きる未来を作るきっかけになれば。この本には、そんな思いが詰まっています
著書の特色
著書は認知症のある方が経験する出来事を「旅のスケッチ」と「旅行記の形式」にまとめ、楽しみながら学べるストーリーになっています
構成は
| 1.乗るとだんだん記憶を無くす ミステリーバス 2.視界も記憶も同時にかき消す深い霧 ホワイトアウト渓谷 3.誰もがタイムスリップしてしまう住宅街 アルキタイヒルズ 4.メニュー名も料理のジャンルもない名店 創作ダイニングやばゐ亭 5.イケメンも美女も、見た目が関係ない 顔無し族の村 6.眼の前に突如現れる落とし穴、水溜り、深い谷 サッカク砂漠 7.熱湯、ヌルっ、冷水。入浴するたび変わるお湯 七変化温泉 8.人面樹、無人の森から聞こえる歌声、動き出す枝 パレイドリアの森 9.時計の針が一定のリズムでは刻まれない トキシラズ宮殿 10.一本道なのになかなか出口に辿り着かない 服ノ袖トンネル 11.距離も方角もわからなくなる 二次元銀座商店街 12.ヒソヒソ話が全部聞こえて疲れてしまう カクテルバーDANBO 13.記憶、計算、注意、空間・・支払いに潜む数々の罠 カイケイの壁 |
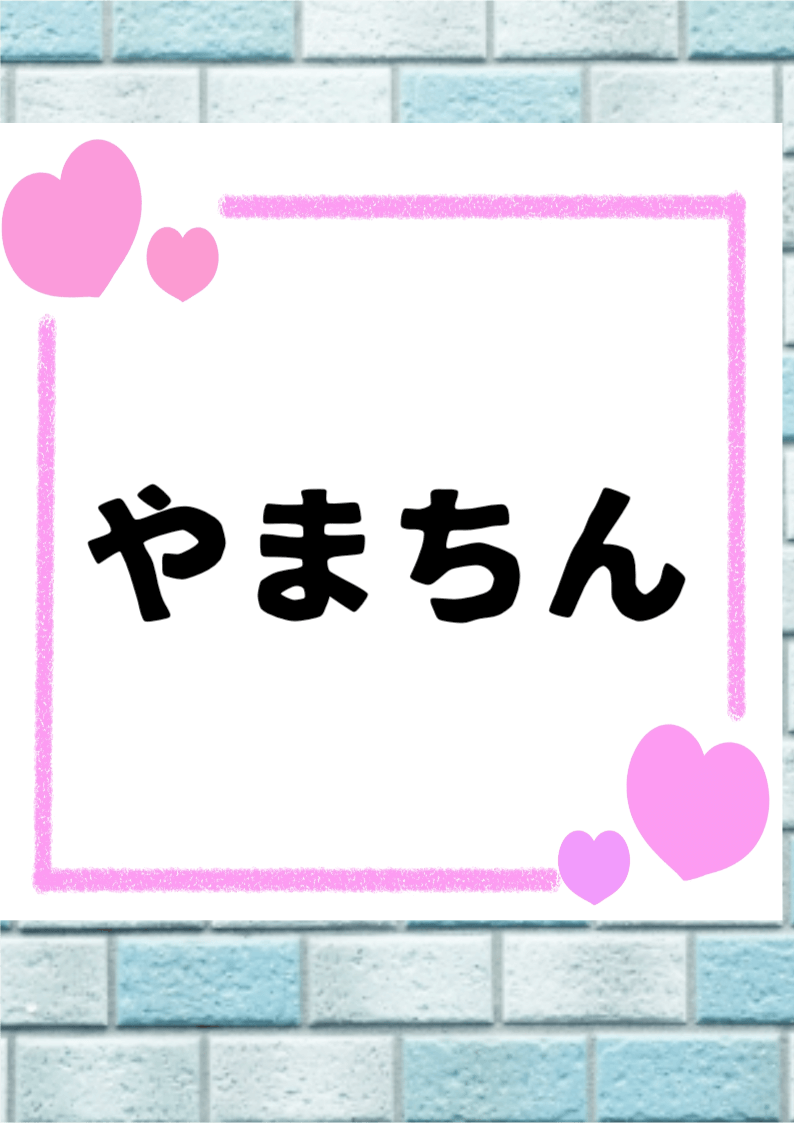
タイトルが秀逸✨
ストーリーを通して認知症状を解説
なぜそれが起こるのか・・
その時のご本人の心理状態は・・
障害が原因と考えられる生活の困りごと・・
例え話や図解を交えて説明してくれるので、とてもわかりやすい❗️
何より介護系の本に多い、堅苦しくて文字ばっかりで読みづらく、退屈で寝落ちということがない
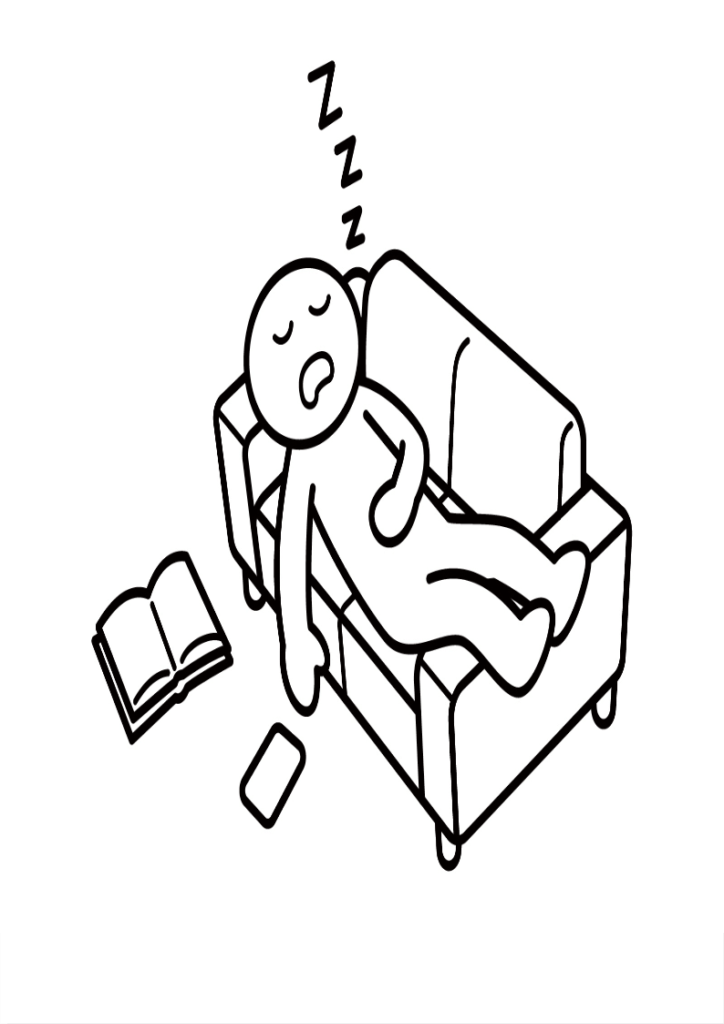
一つのストーリーが20ページいかないくらいなのでスラスラ読めます
全体を通しても300ページいかないので2〜3日くらいで読破できますね
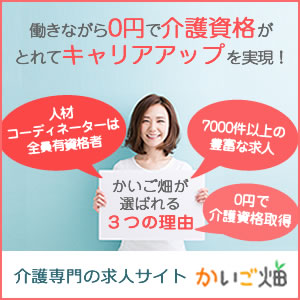
印象に残ったフレーズ
「お風呂に入りたくない」の背景には身体感覚のトラブルで極度に熱く感じる、浴槽に入るとぬるっとした不快な感覚があるという方もいます。空間認識や身体機能のトラブルで服の着脱が困難。「お風呂に入ったばかり」という時間感覚のズレや記憶の取り違えの場合もあります
着替えを拒む、同じ服ばかり着たがることがあります。しかしそれは、1つの服に執着しているわけでも、着替えが嫌いなわけでもありません。実は「服の脱ぎ着が難しく、できるだけ着やすい服を着たい」という気持ちが背景にあることが多いようです
幻視はレビー小体型認知症に特有の症状と言われています。人が本当にいるかのように振る舞ったり、突然現れた虫に驚いたりするのは異常な行動ではなく正常な反応だ、ということです。本人には実際に見えているのですから
両手に物を持っていると、捨てる物と捨てない物が混同する。右手に持っていた空きボトルを捨てるつもりが、気づいたら左手に持っていたスマホをゴミ箱に捨てていた

移動中キップを無くしたり、外出先でカバンやコートを置き忘れたりする。スーパーでは乗って行った自転車や袋詰めした商品を置いてきたりする。家ではリモコンや携帯をどこに置いたかわからなくなる

著書を読んだ感想
『認知症世界の歩き方』を読んだ僕の率直な感想ですが
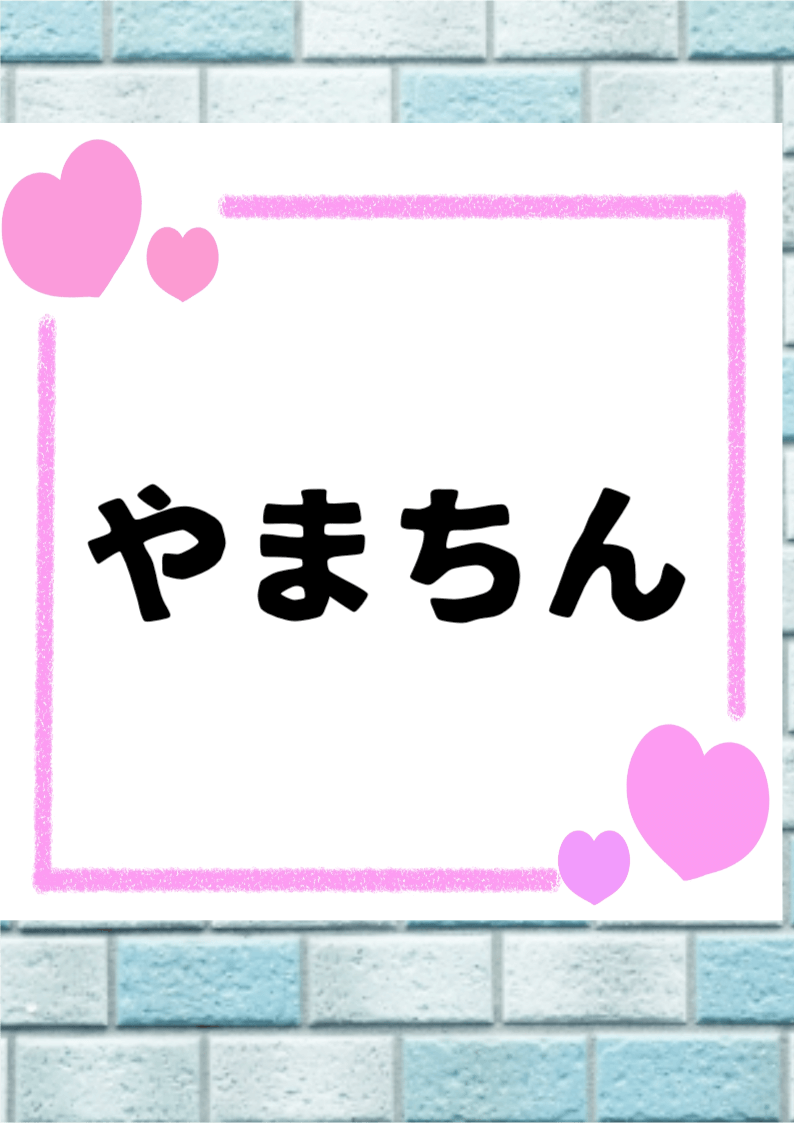
僕にはこの本から新たに学べたことはほとんどなかった
辛辣ではありますが別に著書の内容が薄かったというわけではありません
認知症についてストーリー仕立てでわかりやすく解説されていました
今まで読んだ介護や認知症関係の本に比べればはるかに読みやすい
それでも新たに学べたことがほとんどなかったのは、単に僕が知りたかったことと著書のターゲットがマッチしなかったからだと思います
僕が思うにこの著書のターゲットは
| 7〜80代になり、もしかしたら自分も認知症になってしまうかも・・。認知症になると、どうなるんだろうと思っている方 自分の親が認知症かも、もしくは親の介護が必要になってきたけど「認知症ってなに?」と思っている方 いざという時に慌てないように今から認知症について勉強しておきたいという方 介護の仕事を始めたばかりで認知症に対しての知識がまだ少ない方 |
このような方々にすごく刺さると思います
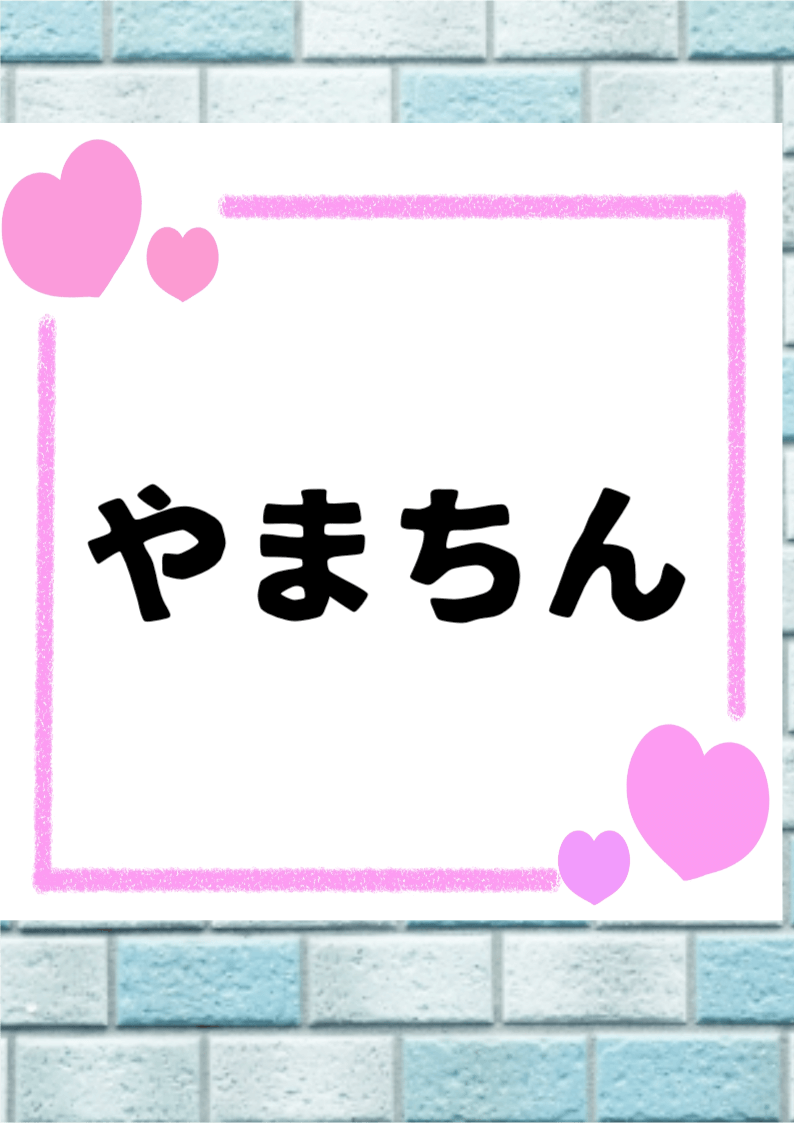
僕自身、両親や兄にこの本を読んで欲しいなと思いました
逆に長く介護の仕事をされている方にとっては、入浴拒否や物盗られ・家族を別人と思いこむなどは
「ある、ある」と共感する一方で
その先を求めているのではないでしょうか
要は具体的にどんな対応をすればいいのかが知りたいのです
認知症と言っても人それぞれで一括りにはできないので「こうなったら、こう」と断定することは出来ないにしても、いくつか提案があってもいいのかなとは思いました
著書を読んでいて「認知症ケアで明日からこれは使える!」というような記述はほとんどなかったです
これが僕の中で満足度が低かった理由で、ひとえに僕が知りたかったことと著書のターゲットがマッチしなかったから
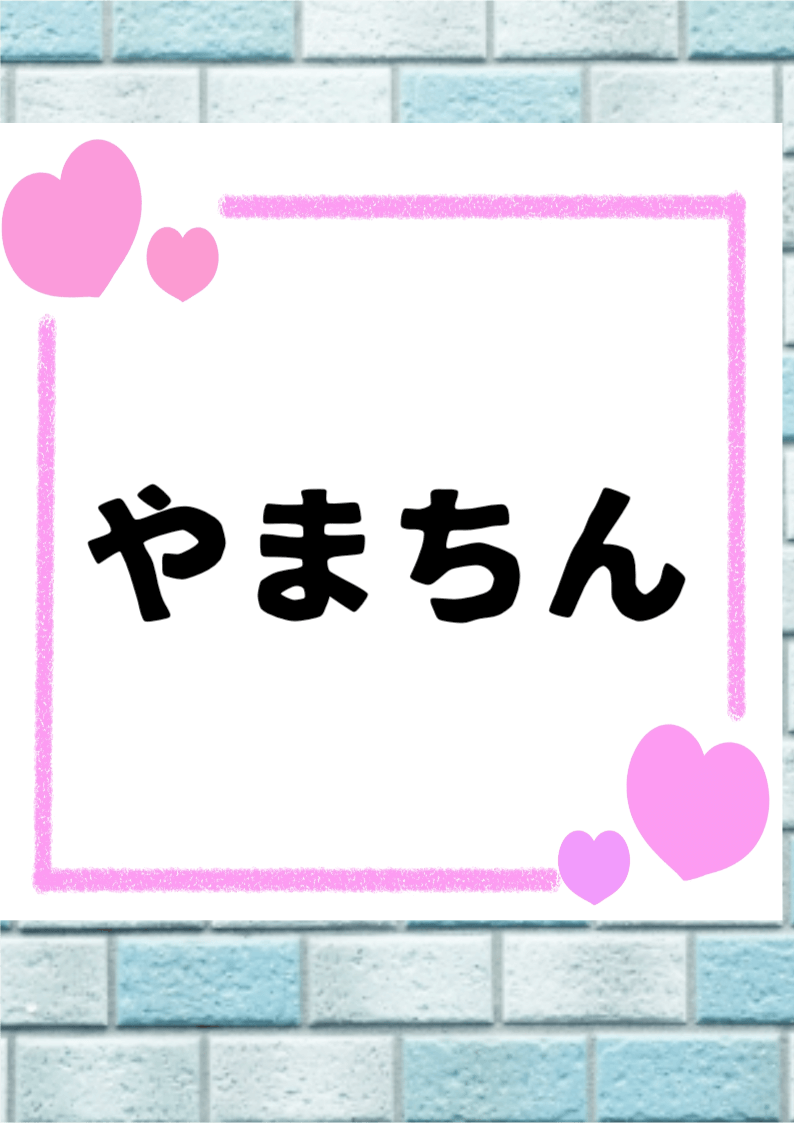
施設の勉強会の資料にするのも、ちょっと厳しいかも
そういう意味では評価が分かれやすい本なのかなと感じました
ただ繰り返しになりますが認知症関連の本は大概が堅苦しくて読みづらい・・
その中でこういうストーリー仕立てで読みやすい本があるということは貴重だと思います
願わくば大学時代にこの本と出会いたかった(*´Д`*)
そんな一冊でした♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました
良かったら他の記事も読んでくれたら嬉しいです❗️
| 宣伝コーナー |
※介護系の資格取得ならユーキャンがオススメ٩( ᐛ )و
ユーキャンのテキストは図解やイラストが豊富で初心者の視点でわかりやすく解説されていて、効率的に勉強を進めることができます
項目ごとに実践課題もあったりして、その都度自分の理解度を知ることも可能
また添削を提出すると講師からのコメント付きで返ってきたり質問をすることもできます
そういったサポートがあるのもユーキャンの魅力✨

ユーキャンについての記事はコチラから

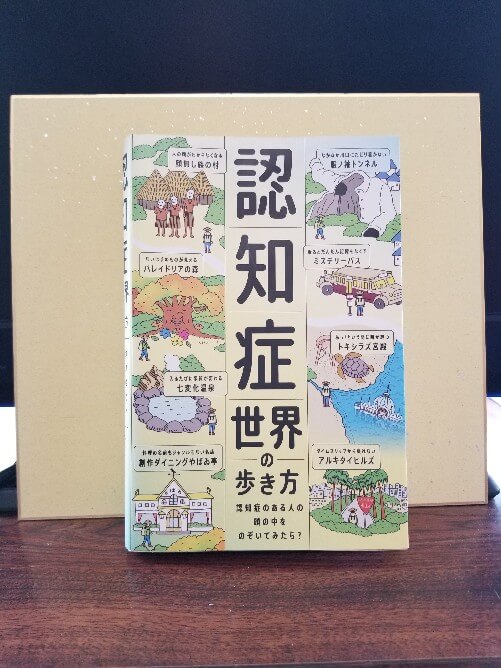





コメント